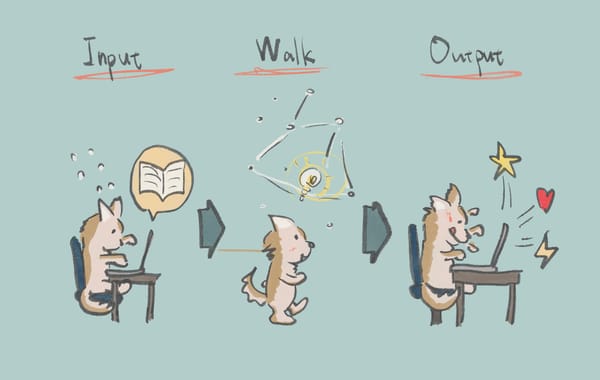個人開発だからこそ出来るユーザサポートがある

個人開発だからこそ出来るユーザサポートがある
この記事はHacker Noonに寄稿した「Personal Developer Can Beat Big Company with User Support」の日本語訳です。
個人開発者は大企業にあらゆる面で常に負ける。果たして本当にそうだろうか。大企業はその大きさゆえにとにかく遅い。でも小さなプロダクトは小回りがきく。個人開発者はとりわけユーザサポートで、大企業に勝る素質がある。
自分はフリーランスをしながらInkdropというMarkdown好きのためのノートアプリを開発している。最近、その売上で家賃の半分が賄えるようになった。アプリを購読してくださっているユーザさんもそれを喜んでくれている様子で嬉しい:
自分がどうやって彼らを惹きつけているか、ユーザサポートの観点でその方法をシェアしたい。
ユーザはサポートの返事があるまで何日も待たされることに慣れきっている。大企業のユーザサポートを受けたことがある人なら分かると思う。電話で待たされ、たらい回しにされ、数日後にやっと回答が得られる。だからメールを送信する時、すぐに返事がもらえるなんてそもそも期待なんかしない。
そんな退屈なサポートが当たり前だと思っている人にもし90分以内に返事が来たら、彼らは間違いなく驚く。彼らの不満げな態度はそれだけで180度変わる。自分はもしサポートメールを受け取ったら、その時やっていた作業を可能な限りすぐに中断して返信するようにしている。早い時は数分程度で。するとユーザさんはこう返事してくれる 。 “Thank you for the quick response”と。
もしすぐに回答できないような問い合わせが来ても、とにかく何か返事をする。明確な答えが出るまで保留にするのは良くない。だって相手はその間ひたすら待たされているんだから。つまり即レスを心がけるだけで、ユーザに確実に好印象を与えられる。
たとえ個人開発であっても、アプリは自分一人で作っているわけではない。ユーザのフィードバックがあるお陰で気付かなかったバグが直せたり良いアイデアをもらえたりする。だから、貢献してくれたユーザを称えるのは当然のことだ。もし自分の報告したバグが直って、さらに作者がその事を賞賛してくれたらすごく嬉しい。でも残念なことに、ほとんどのサービスは実践していない。なぜなら、大企業ではそれをやるにはキリがないほど沢山の顧客がいるから。
自分はInkdropの新しいバージョンをリリースした時、リリースノートに必ず貢献してくれたユーザの名前を記載するようにしている:
自分がもともと予定していた機能だろうが、既に気づいていたバグだろうが関係ない。ユーザが何かしらその改善に関わっていれば、賛辞を末尾に付記する。この手法はとても効果的。
この手法はお金がかからない上に簡単に出来る。しかも、ユーザの立場からすると自分がサービスに貢献できた証拠になる。まるでオープンソースに貢献できた時みたいに嬉しいし、周りに自慢したくなる。その上、サービス側はちゃんとユーザの声を取り入れているというアピールにもなる。
もちろんこれはユーザの声に迎合しろという意味ではない。この記事で書いたように、自分が本当に必要だと思った機能だけを検討するべきで、そう思えなければどんどん断っていい。
できない約束はしない。それは周りの人間関係でもそうだろう。ユーザに機能要望を受けた時、 “It’s coming soon..” とつい言いたくなるけど、それは本当に対応の目処が立っている時しか言うべきじゃない。誠実で友好的な態度は、ユーザがプロダクトを信じやすくしてくれる。悪意のない嘘でもつくのはやめよう。
参考になれば嬉しい。