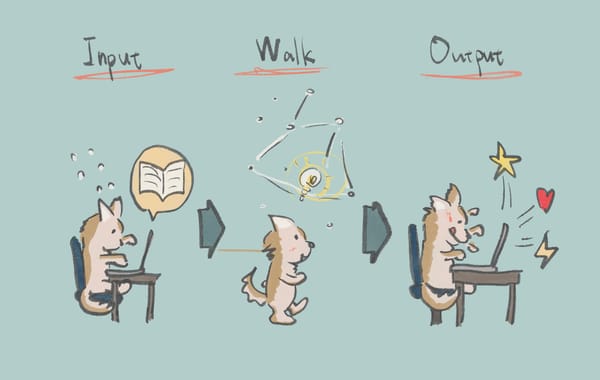秋の岐阜旅行に行ってきた

秋の岐阜旅行に行ってきた
下呂温泉・白川郷・高山を4泊5日でぐるり
11月は自作アプリを開発しつつ、知人の会社の開発を手伝ったりしていました。まるっと任せてもらえると本当に仕事がやりやすくてありがたい。その合間を縫って、中旬に4泊5日の岐阜旅行に行ってきました。そこで撮った写真をダイジェストでご紹介したいと思います。
ちなみに、この間のユーザサポートも24時間以内に対応してました。

下呂は東京より体感では4〜5度くらい寒くて、今年初めてマフラーを巻きました。温泉は肌がびっくりするぐらいツルツルになりました。自分アトピーなんですが、それにも効くらしいです。療養するには2日の滞在では足りないですね。

道行く旅行客はまばら。いつもこんなもんなんですかね。本当に田舎町という感じで、都会の喧騒を忘れられます。

山奥の地だけあって天候の移り変わりが早く、さっきまで降っていたと思った雨がいつの間にか止んでいたり。空気が霧っぽかったり澄んでいたりと、自然の表情の豊かさが感じられます。


部屋食での旅館の料理、本当にこういうの久しぶりで、おいしさを噛み締めました。
合掌造りの家は白川郷だけかと思いきや違うんですね。下呂温泉中心地から15分くらい歩いたところに、合掌村という観光施設があります。ここでも合掌造りの家を見ることが出来ます。中に上がって囲炉裏を囲んだりしました。あたたかい。


20年以上ここで働いているというおじさんが尺八で民謡を吹いて聴かせてくれました。「吹いてみ」と言われ、予期せぬおじさんとの間接キッスに抵抗を覚えつつトライ。案外あっさり音が鳴りました。「管楽器やっとったんか?」と訊かれたので、鳴らなくて苦心するのを期待されてたのかな。管楽器経験は全く無いですよ。

下呂から電車で一旦高山まで行って、そこから濃飛バスで1時間弱揺られて白川郷へ。天気が最高。
上の写真は荻町城跡展望台で撮ったんですが、村から30分置きぐらいでシャトルバスが出ています。

白川郷は完全に観光地ですが、その合掌造りの家の一部ではまだ実際に住んでいる人もいます。


木を縄でしばるという原始的なアーキテクチャに痺れます。メンテナンスが大変そうですね。


囲炉裏の周りは凄く暖かくて寝そうになります。



高山はグルメスポットが豊富で、食べ歩きをしている人が多くいました。飛騨牛の串焼きを頬張りながら歩く人がいたり、みたらし団子、牛肉まんなどなど食欲をそそるお店が立ち並んでいます。



高山ラーメンが有名らしく、お昼に食べました。訪れたのは「麺屋しらかわ」。行列になっていて1時間ほど並びました。味は・・正直並ぶほどでは無かったかも。でも店員さんが長い待ち時間をとても労ってくれて親切でした。

来る前はあまり期待していなかったけど、結構楽しかったです。

最終日は名古屋で一泊しました。下呂や高山で過ごした後に名古屋に行くと「都会や!」と感じますね。夜なのに明るい。
晩飯はGoogleマップで点数が良かった「鳥八」へ。ここ、めちゃくちゃお薦めです。小じんまりとした飲み屋なんですが、ホールとキッチンの二人だけで忙しそうに回していました。でも対応が凄く丁寧かつ速い。働いている様子を見ているだけで楽しめます。味ももちろん最高。


今回の旅行では、カフェやレストランを探すのにGoogleマップのレビュー情報を結構参考にしました。一昔前は全然アテにならないくらい情報が少なかったんですけど、今はかなり充実してますね。海外の旅行者の評価も読めて面白いし。
日本においてレビューサイトの代名詞と言えば食べログです。その分影響力が大きいので、点数の良い店は大抵混み合います。一方、その食べログでは高くないけどGoogleマップでは良い評価のお店が結構あったりします。そのお店は結構狙い目です。マップ上で点数のいいやつだけをフィルタして表示する機能も付いているので、探し易さも◎。
今回Googleマップの情報に助けられたので、自分も何個か投稿してみました。色々バッジが付いたりして楽しいですね。
以上、岐阜旅行記でした。白川郷はこれから雪景色が綺麗になる季節なので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。