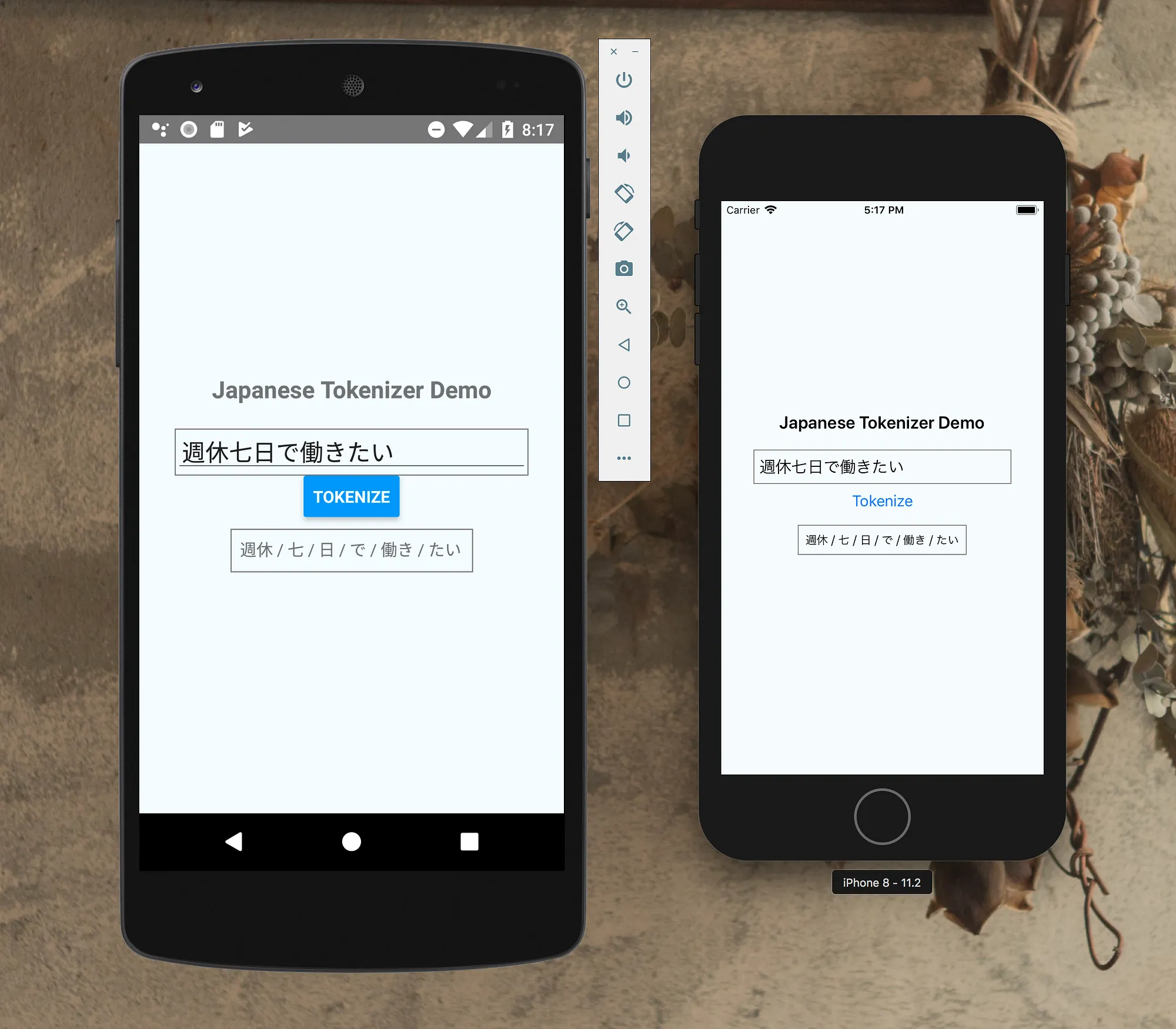Imported-from-Medium
GDPR対象業者の判断基準とプライバシーポリシーを書く際のポイントまとめ
GDPR対象業者の判断基準とプライバシーポリシーを書く際のポイントまとめ MarkdownノートアプリInkdropを一人で開発しているTAKUYAです。InkdropはEUにもユーザが結構いるので、GDPR (EU General Data Protection Regulation)への対応準備を進めていました。GDPRはEUの個人情報保護に関する新しい法律です。この度、施行予定日の2018年5月25日に無事間に合わせることができました。 プライバシーポリシーをイチから書き直し、曖昧な表現を避けて、GDPRで要求されている個人情報取り扱いに関する情報を全て開示しました。書くの大変だった・・。 先日、GDPRに関する自分用のメモとして以下の記事を書いたら、予想以上に反響が大きくてびっくりしました。日本語で開発者向けの分かりやすくまとまった情報が無いのがまず問題ですね。 本稿では実際に対応してみて分かったことや、プライバシーポリシー準備の注意点などをシェアしたいと思います。これから対応される方の参考になれば幸いです。 Inkdropは今回GDPR対応したものの、GDPR対象業