Inkdrop紹介プログラムを始めます 〜 広告にお金はかけない

Inkdrop紹介プログラムを始めます 〜 広告にお金はかけない
$2.5贈って$2.5を貰おう/自分がされて嬉しい方法で喜ばせたい/広告会社に払うぐらいなら貢献してくれた人にお返ししたい
English version is available here.
どうもInkdropのTAKUYAです。InkdropはMarkdownのノートをデバイス間で簡単にオーガナイズできるアプリです。マーケティングを含め、このプロダクトを僕は一人で取り組んでいます。Inkdropのマーケティング戦略は基本的にこのブログに頼ってきていて、幸いそれは今のところ上手く行っています。そして現在、いくつかの広告を走らせるには十分な売上が立つようになりました。しかしながら、広告は今後も出そうと思っていません。なぜなら好きではないからです。その代わり、紹介プログラムの提供を開始したいと思います。本稿では、自分がなぜ広告費をかけるのではなく紹介プログラムを提供することに決めたのか理由をお話しします。
$2.5贈って$2.5を貰おう 🙌
紹介プログラムの仕組みはいたってシンプルです。あなたが紹介したすべての人に$2.5分の利用クレジットが付与されます。彼らがフリートライアルを終えて初めて課金した時、あなたにも$2.5分の利用クレジットが与えられます。これは月額利用料($4.99)の半分に相当します。紹介を通じて得られるクレジットには上限がありません。獲得したクレジットは自動的に次回の支払いに適用されます。あなた用のユニークな紹介リンクはこちらから取得できます。このリンクをぜひ友達や同僚、フォロワーにシェアしてください。
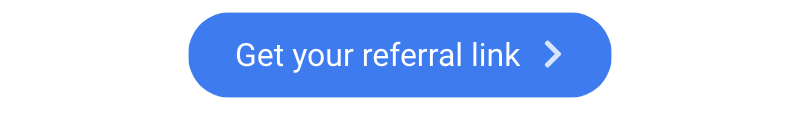
自分がされて嬉しい方法で人を喜ばせたい
ところで、あなたは眠る前に「明日はどんな素晴らしい広告に出会えるだろうか」と想像したことがあるでしょうか。僕はありません。なぜなら広告は(僕にとって)鬱陶しいし、邪魔だからです。だから僕は広告をうまく活用できないし楽しむことも出来ません。一度だけ過去にTwitterで広告を出してみたことがありますが、全く面白くありませんでした。お金で人々のタイムラインを盗んでいるような気持ちにすらなりました。なのですぐに止めました。思い返してみれば、上手く行った施策はすべて自分がされて嬉しいことばかりでした。それはそうです、なぜなら「自分がされて嬉しいこと」なら詳しく想像できるし、ユーザに対して上手く実行出来るからです。僕のブログマーケティングがなぜ上手くいったかと言えば、それは単純に「昔の自分が知りたかった事」を書き続けたからです。
しかし単一のチャネルに依存するのは脆弱です。ブログマーケティングは文章を読むのが好きな人や、自分が書けるトピックに興味のある人にしかリーチできません。では、Inkdropのマーケティングをこの先どうすればよいでしょうか。
広告会社に払うぐらいなら貢献してくれた人にお返ししたい
Inkdropを始めた当初との大きな違いは、現在1,500人もの顧客がいることです。彼らはたまに「アプリを同僚/友達におすすめしたよ!」と言ってくれます。Inkdropは彼らの口コミがなければここまで成長することは出来なかったでしょう。感謝してもしきれません。しかし、他にお礼する方法がないので、ただ「ありがとう」と言うだけでした。
最近、プラグイン開発者ライセンスを発表しました。これは、プラグインを作ってくれた方は永久無料でアプリが使えるようになるというライセンスです。それから沢山のプラグインが公開されました。僕は彼らが素晴らしいアイデアとスキルを持っていることに驚きましたし、一緒にアプリをよりよくすることを楽しんでいる様子が伺えてすごく嬉しかったです。このプロダクトはニッチですが、そのコミュニティは徐々に熱を帯びつつあります。もっと盛り上がらせたい。ただ一方で問題もあります。それは、もしコミュニティに貢献したいと思っても、みんな必ずしもいいアイデアや作るスキルを持っていないという事です。
これらの問題を解決するには、紹介プログラムがいいのではないかと僕は考えました。それはユーザさんにアプリの事についてブログを書いたり人に教えるいいインセンティブになり得ます。特別なスキルもいりません。はい、それは上記で述べたような、既に起こっている純粋な口コミに影響を与える可能性があります。一部の人はこのような動機づけられたシェア行動が好きではないでしょう。でも僕は個人的に普段から、よくアプリや家電やカフェについて自分のブログでレビューしています。その記事にはアフィリエイトリンクを貼っており、そこからたまにお小遣いが入って嬉しかったりします。紹介プログラムはまさにそれと同じです。少なくとも紹介クレジットのお金は、あなたのオンライン行動をトラッキングするような人たちのポケットに入れるよりずっと良いと思っています。もちろん、あなたはこれに賛同する必要はありません。なぜならすべての人を満足させるのは不可能だからです。僕はこの紹介プログラムで何が起こるのか見てみたいのです :) 一緒にコミュニティを育てましょう!




