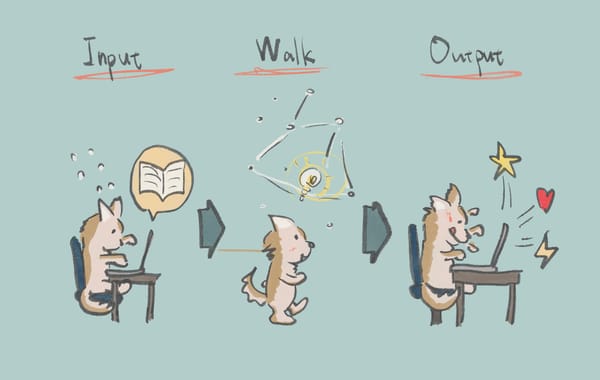個人開発者が会社作るならアメリカより日本の方が結局よさげ

個人開発者が会社作るならアメリカより日本の方が結局よさげ
情報が少なくて調べるのに時間がかかりすぎるから
こんにちは、個人アプリ作家のTAKUYAです。確定申告の季節ですね。
今作ってるMarkdownノートアプリInkdropの売上がそれなりに立つようになってきました。去年の売上は393万円でした。という訳でぼちぼち法人化を検討しています。ちなみに今は個人事業主です。
Stripe Atlasを利用してアメリカに法人設立しようと思ったんですが、いろいろ調べた結果、結局やめることにしました。その判断に至った経緯をシェアしたいと思います。
法人化する主なメリットは以下の通りです:
- 無限責任から有限責任になる。もし多額の負債を作っても会社をたためば自己破産しなくて済む
- 1
- 法人用の住所が設定できる
- 売上が1,000万円を超えると消費税課税事業者になる。法人化することで日本では最初の二年は消費税の課税が免除される
売上から経費や控除を差し引いた額が課税所得です。個人事業者としては使ったお金をいかに事業と結びつけて経費とするかが節税のポイントになります。その所得が330万円を超えてしまうようであれば、法人化した方がお得という事ですね。
そして無限責任から有限責任になることで、安心して事業を拡大できます。
ちなみに自分の場合は法人形態はLLC(合同会社)がよいと考えています。なぜなら投資を受ける予定もないし、一人でこじんまりと経営して行きたいからです。
でも日本での法人設立はとにかく面倒で退屈です。印鑑を作ったりとか。なんとか楽出来ないかなと思ったところにStripe Atlasの存在を思い出しました。これは日本にいながらにしてアメリカのデラウェア州に法人を設立できるというサービス。迷ったら面白そうな方を、という訳で調べてみることにしました。
デラウェア州に登記する作業もすべてオンラインで完結します。めっちゃ手軽です。住所も与えられるので、わざわざシェアオフィスの住所貸しサービスを利用する必要がありません。コスパすごい。
去年の8月からC-CorpだけでなくLLCの設立にも対応しました。
Inkdropのカード決済は既にStripeを利用しています。つまり僕のStripeアカウントには既に多くの顧客情報が紐付いているわけです。Stripe Atlasでは、設立したUS法人用のアカウントが新たに発行されます。なのでアカウントの移行が必要そうです。
問い合わせたところ、Stripe内藤さんから以下の回答をいただきました:
移行可能: 顧客情報および保存されたクレジットカード情報 https://dashboard.stripe.com/customers移行不可: 決済、インボイス、定期支払い、クーポン、ログ、イベントなどの履歴や一覧詳細はこちらにございます: https://support.stripe.com/questions/how-can-i-migrate-to-a-new-stripe-account
つまりアカウントをまるっと移行するのは不可能で、こちらでAPIを使って慎重にサブスクリプションを移行する必要があるようです。絶対事故りそうです。やりたくない。現アカウントの契約はそのまま運用して個人事業主の売上として計上するのが現実的な気がしました。
LLC では、法人の段階での課税がありません。 法人が稼いだ利益は、そのまま出資者である社員に配分されたと考え、社員の所得税としてのみ課税されます。 課税の対象である利益が法人を通り過ぎる(パス・スルー)という考え方から、これをパス・スルー課税と呼びます。
二重課税を避けるパス・スルー課税の場合、連邦税を申告する必要はないようです。
日本の税制上、外国法人としてみなされます。利益をUS法人の口座から自分個人の口座に移した時、そのお金を海外からの所得として申告します。
日本の居住者(アメリカの非居住外国人)または日本法人が、アメリカのLLC有限責任会社の出資者である場合、米国側ではほかの出資者と同様に、純利益、損失、控除などの出資比率に基づく持分金額を報告して確定申告する義務があります。日本側では、LLC有限責任会社からの利益分配を受けた場合にだけ、海外からの所得として申告することになります。
その利益分配したお金には外国法人税が課税されるようです:
パス・スルー課税を選択した米国LLCのような事業体から構成員である内国法人が分配される所得の金額(自らに帰せられるものとして計算される金額)は外国子会社配当益金不算入制度の対象となり、また、こうした事業体が本制度の適用対象となる外国子会社に当たる場合に、その外国子会社から利益の分配があるときのその所得の分配額が確定した段階で構成員に対して課される外国法人税の額についても、損金不算入となる外国源泉税等の額に該当することとなる。
その分配される利益に対しては外国税額控除が受けられます。これで二重課税が避けられるという訳ですね。
Googleで日本人でStripe Atlasを利用した人はいないかと検索したところ、xarshさんのブログを見つけました:
いくら探してもこの記事しか見つかりませんでした。実際に使っている人がいるならもっと記事があってもいいはずです。この記事は2017年10月に執筆されたもので、一年以上経過しています。
設立は簡単でも、その後の運営は実際どうなのかが気になったのでxarshさんにメールで質問してみました。すぐに回答してくれて、とても助かりました。この場を借りて感謝します。いただいた回答は概ね以下の通りです:
- 基本的にStripe Atlasが毎年納税時期に案内してくれるほか、丁寧なドキュメントが閲覧できるのでそれに法っている
- 具体的な作法や税法についてはStripe Atlasと提携している会計事務所がフォーラムで相談に乗ってくれる
- 税務と法務に関してのプライベートな相談を安価で受けられるようなプランが設定されている
- しかしながら面倒な思いをしたことは数多く、最初から日本で登記しておけばよかった
- デラウェア州の役所はメールの返信も早く、確かにこれは便利
- 結局日本で会社を立ち上げた方が日本国内にいる場合はたくさんのノウハウもあるし投資したいと言ってくれる人々とも知り合えた
- アメリカのスタートアップの作法みたいなページをたくさん調べて手続きする手間を振り返るとちょっとな…という感覚
確かに、現時点で自分も前述の情報を調べるだけなのにめちゃくちゃ時間がかかって苦労しました。いくらフォーラムで相談できるとはいえ、そこに時間が多くかかっては本末転倒です。Stripeのアカウント移行もリスクが高いし、今回はStripe Atlasの利用を見送ることにしました。
お世話になっているStripeにはネガティブな内容になってしまったかもしれません。ただ、もしこの記事が目に留まったらサービス改善の役に立てて欲しいと願っています。課題はなんといっても情報不足です。
法人化する目的は最初に述べた通りで、そのメリットが享受できれば形態は正直何でもいいです。「アメリカで会社を経営してます」なんて言うとかっこいいですが、見栄は一円にもならないので却下です。
という訳で、自分が法人設立するなら日本で合同会社になりそうです。今すぐ立てる必要は無いので、また書籍を買ってじっくり勉強しようと思います。